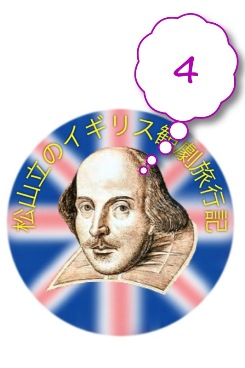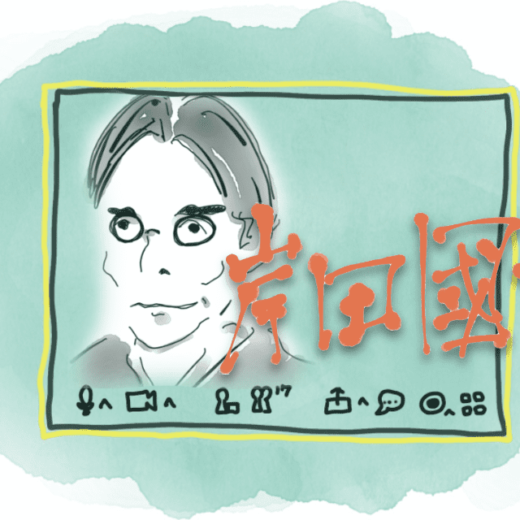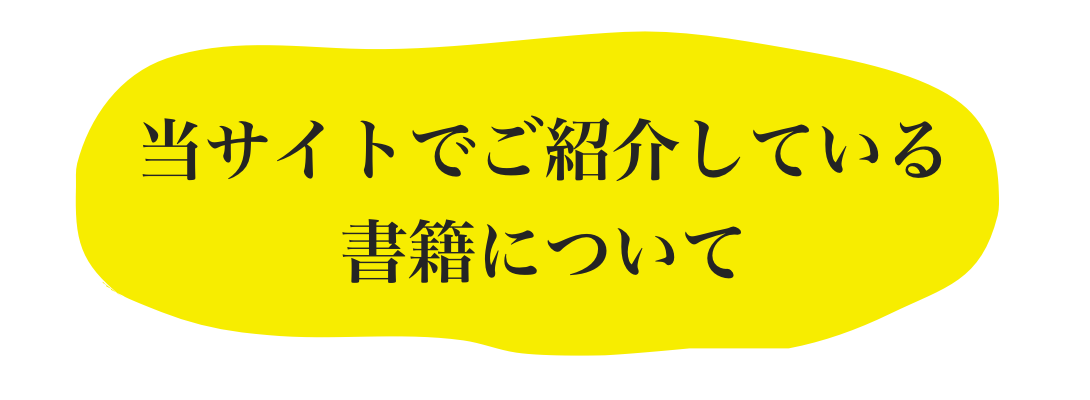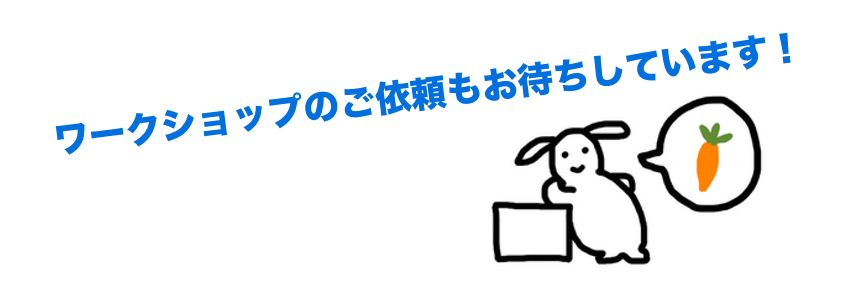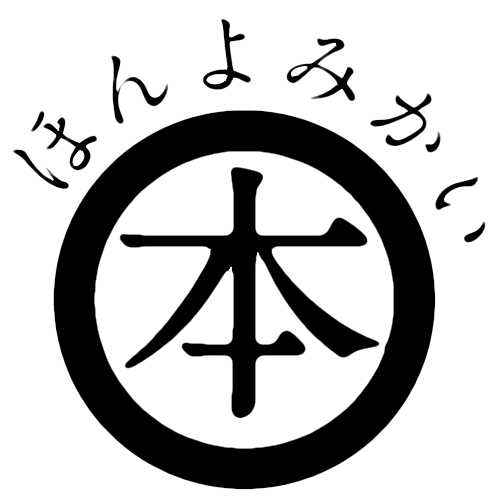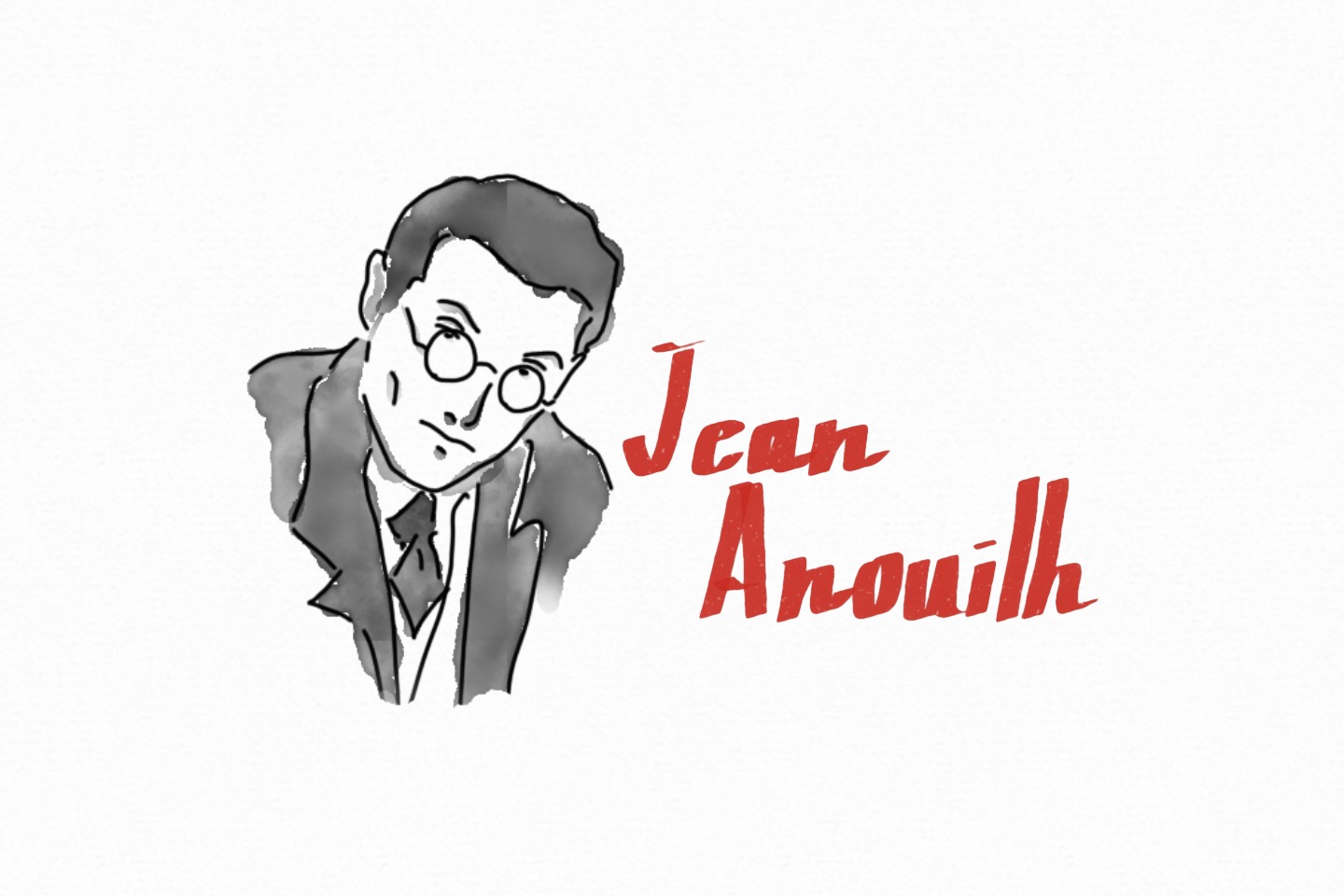
うだるような熱帯夜が過ぎ、秋の虫の音が聞こえる今日このごろ。今回も対面開催の『本読み会』です。このまま対面開催を基本線にしようかな…と、微減するコロナを横目に、懲りずに戯曲を読んでおります。最近はもっぱらギリシャ戯曲とキリスト教戯曲を行ったり来たりしておりますが、今回はギリシャ劇に端を発する名作戯曲、ジャン・アヌイの『アンチゴーヌ』に挑戦です。
アンチゴーヌは、かつてテーバイの王だったオイディプスの娘。オイディプスには、イスメネ、アンティゴネ(アンチゴーヌのこと)という二人の娘、それからポリュネイケスとエテオクレスという双子の息子がおりました。ところが、二人の息子は王位継承争いで互いに刺し違えて死んでしまい、ポリュネイケスの方は死体も埋葬されない始末。アンチゴーヌは人目を盗んでは墓場へ行き、野ざらしの兄の死体に土をかぶせようとする・・・というお話が下敷きにあります。このテーバイ王家というのは、ともかくろくなことが起きません。
序詞役(劇の始まりを告げる前口上をいう人)の「ごらんのとおりです。この人物たちがこれからみなさまがたにアンチゴーヌの物語を演じてごらんに入れるわけです。」から始まるこの戯曲は、文字通り俳優に登場人物という役割を与え、観客に物語を見届ける役割を授けます。演劇は役割を演じる芸術であることを強く意識させ、それがアンチゴーヌをはじめとする登場人物が背負う運命(=役割)とも重なり合うように描かれます。
『アンチゴーヌ』で最も苛烈な対話は、やはりアンチゴーヌとクレオンの対話です。法に逆らって兄を埋葬しようとするアンチゴーヌと、それを禁じるクレオン。ここの対話の面白いところは、アンチゴーヌだけではなく、クレオンの人間性が深く掘り下げられている点です。クレオンは今や国王ですが、自分はライオスやオイディプスほどのカリスマ性ある君主でないことを自覚しています。クレオンは自分の限界に向き合っている。だからこそ、ポリニス(オイディプスの子、アンチゴーヌの兄)の死を使って物語を形成し、国を統治するために使う必要に駆られています。ちょうど「国葬」で揉めている我々としては耳の痛いシーン・・・。
それもそのはず。この戯曲が書かれたのは1942年。フランスがナチスドイツによって占領下に置かれていた時代です。アヌイはフランスがドイツに融和的な態度を取ることを舌鋒鋭く批判するべく、この『アンチゴーヌ』を書いたと言われています。表面上はギリシャ悲劇の焼き直しをしているようでも、時代と状況を考えれば、フランス国民にはアヌイの書こうとしたことがまるで犬笛のように聞こえたことでしょう。クレオンのバランス政策にも一理あるものの、やはりアンチゴーヌの掲げる理想を手放してはいけないのではないか…やっぱり戯曲は時代の中の産物ですね。
今回はわりと大人の(?)参加者が多く、クレオンの言い分に耳を傾ける声が多かったように思います。自分の有限性に否が応でも直面し、妥協しなくてはならないこと。個人としては納得いかなくとも、組織人としては理解しなければいけないこと。ギリシャ悲劇を題材にしていることを忘れるほど、私たちの生活に密着した葛藤が描かれています。これがもっと若い学生や高校生が読むと、ぐっとアンチゴーヌ目線で読むことになるのでしょうか。
物語を示すこと、政治的な姿勢を表明すること、悲劇と喜劇を行き来すること、そして観客を楽しませること…などなど、アヌイは多くをこの戯曲の中で達成しています。秋の夜長、アヌイの他の戯曲『ひばり』『舞台稽古』などにも手をのばしてみませんか。
ギリシャ&キリスト教シリーズ、まだまだ続きます!
(松山)