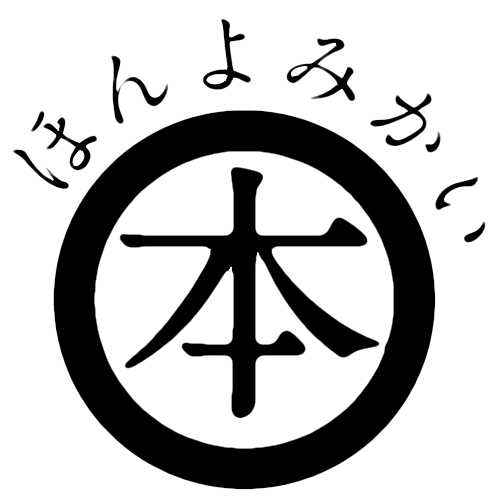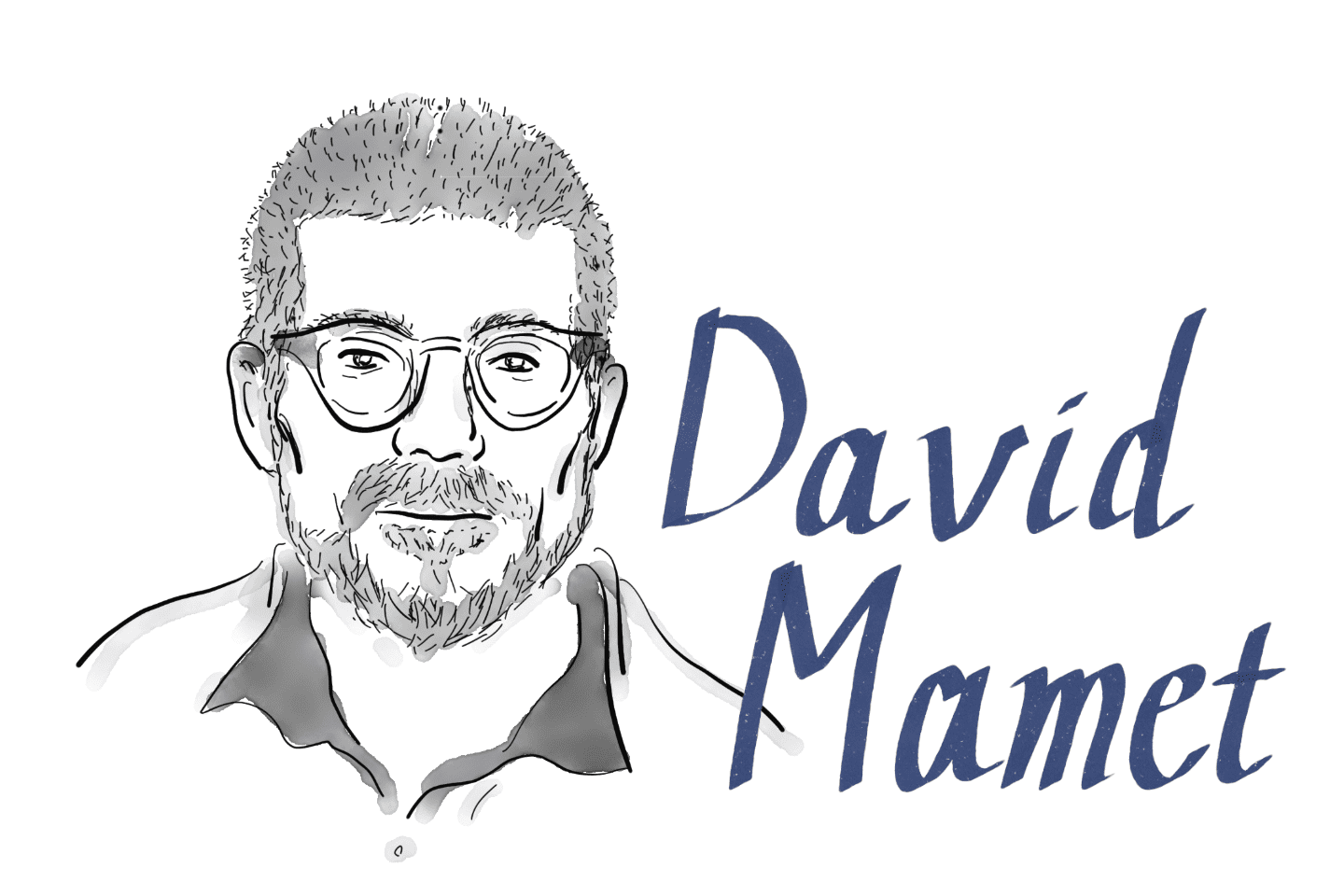
お互いにとって初めての試みです。このたび産声を上げたばかりの『デビッド・マメットを読む会』と、老舗読書会『本読み会』コラボ企画という形で、デビッド・マメットの『オレアナ』を読むことになりました。同じ釜の飯を食う?隣の芝生は青い?隣の店の定番メニューを食べてみる感じでしょうか。いや、ちょっと違うな…。
デビッド・マメット。1984年に発表した戯曲『グレンギャリー・グレン・ロス』でピューリッツァ賞を受賞。その後、同作は『摩天楼を夢みて』として映画化されました。今回の『オレアナ』は、日本でも何度か上演されたことのある二人芝居です。『本読み会』でも時折「マメット、まだ読んでないな」と名前の挙がる作家ですが、ついぞ読むには至りませんでした。
将来有望なジョンはついに大学の終身雇用資格を得るところ。大学教員として研究の環境も経済的な安定も保証されるポストです。彼はこれを機にマイホームを購入しようとしていますが、これはどうもうまく進んでいない模様です。一方、キャロルはジョンの授業についていけず、単位を落としてしまいそうなところまで追い込まれています。教員と学生。持てるものと持たざる者。ジョンに掛け合い、なんとか救ってもらえないかと頼み込むところから舞台は幕を上げます。
先生として紳士的に対応して、キャロルの肩を抱きながら慰めたつもりのジョンでしたが、後日キャロルはジョンをセクハラで訴えます。これによって終身雇用の風向きも怪しい。ふたりは再び会い、互いの主張をくり広げるのですが、むしろ食い違いは広がってゆくばかり。お互いに相手が欲するものが何なのか理解できず、それを相手に与えることができない。食い違いはやがて埋めることのできない分断となり、最後にはジョンの暴力性がむき出しになるところで終わります。まあ、あまり後味のいい幕切れではない。
ふたりは言葉を交わせば交わすほど、分かり合えない存在になっていきます。個人で話しているようでいて、いつのまにか何かを代表して喋り、何かを象徴することによって、目の前の相手と意志疎通を図ることができなくなってしまう。ドラマの根幹にあるのは、「自分の言葉でしゃべる」ということの難しさです。
この分断が、本人にも無自覚に起こっているところに真の怖さがあるのではと思うのです。読み手同士の話の中でも、「キャロルは初めからジョンを陥れるつもりだったのか?」「いや、最後の最後までジョンに何かを期待していたのでは?」と意見が分かれました。読み手によって違う世界が見えてくるのは、いい戯曲の特徴です。
『オレアナ』はアメリカ版とイギリス版で幕切れが違うのも面白いところです。戯曲にも両バージョンが収録されているので、今回は二通りのラストシーンを読み比べてみることにしました。アメリカ版の方はジョンの暴力性がストレートに出ている一方、イギリス版は欺瞞をとことん追及していった挙げ句、ジョンが自己同一性を失っていくような印象を受けました。ちなみに、イギリス版初演はハロルド・ピンター演出。ピンターも作家としてラストに思うところがあったのやもしれません。
実は私も大学で教鞭を執る人間の一人。ジョンとキャロルとの対話は、そのまま現代の大学でも日々起こっているディスコミュニケーションです。読みながら背筋が寒くなりました。
今回は『本読み会』主宰のふたりも、半分参加者として輪に加わりながら戯曲を読んだので新鮮な心持になりました。戯曲の読書会に参加するって、こういう感じなのか…と新たな視点を得た感じ。渡辺さん、いい戯曲をありがとうございました。(松山)