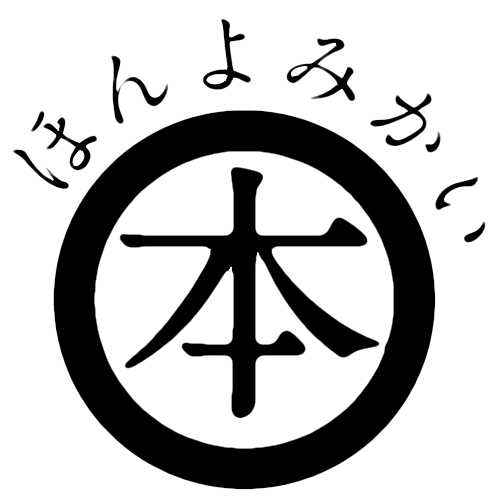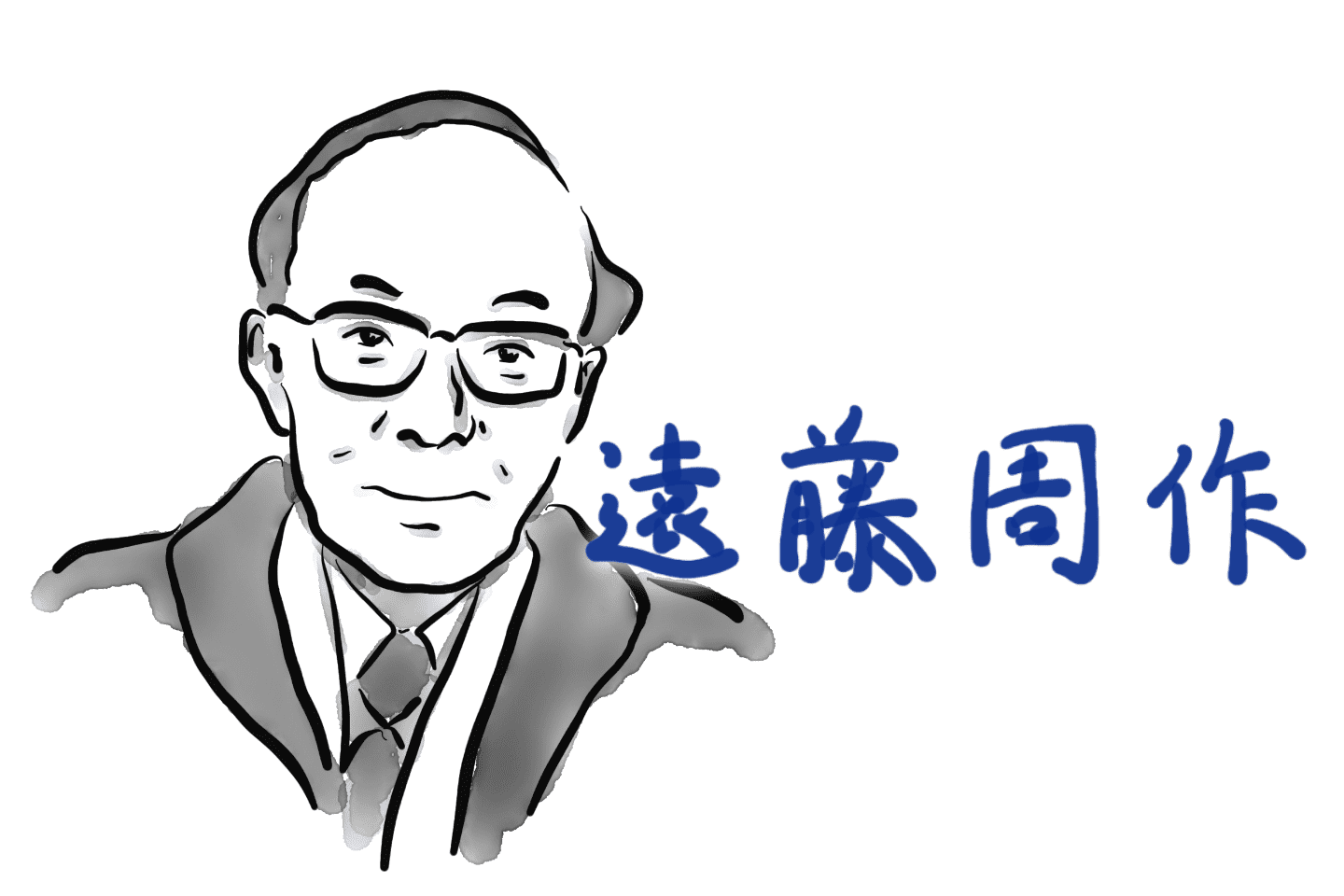
黄金の国と信じてやってきたこの国は泥沼の国だった。しかし・・・。
『本読み会』の送る「日本戯曲で触れる!キリスト教シリーズ」第二弾は、日本を代表するキリスト教作家、遠藤周作の戯曲を取り上げました。
近年、遠藤周作の遺稿が次々と発見され、戯曲も『善人たち』『切支丹大名・小西行長』『わたしが・棄てた・女』の三作が出版されたのは記憶に新しいところです。遠藤周作といえば『海と毒草』『沈黙』『深い河』などの小説が思い浮かびますが、今回は戯曲『黄金の国』を取り上げます。
『黄金の国』は1966年5月、劇団「雲」で芥川比呂志演出によって初演された作品。遠藤にとってはこれが初めての戯曲でした。遠藤自身、「戯曲の書き方はほとんど知らないと言ってよかったから、まず初稿を芥川氏に見て頂いて教えていただいた」(『黄金の国』あとがきより)と書いています。そういわれてみれば、台詞もどことなく小説のような・・・。
発表された順番としては、小説『沈黙』のあとに戯曲『黄金の国』なのですが、『黄金の国』は『沈黙』前日譚にあたり、登場人物もテーマも多くの部分で重なっています。『黄金の国』を読んでから『沈黙』を読むと、ドラマの背景や足跡が感じられてより深く味わうことができるでしょう。何より、小説と戯曲の性質の違いが面白い。小説と戯曲、それぞれが得意とするところと苦手とするところがよく分かります。
さて『黄金の国』。島原の乱の二年後、井上筑後守のもと、長崎では切支丹への取り締まりが日ごとに強まっていました。そこここの村で「踏絵」が行われていた頃です。井上の配下でありながら密かにキリスト教を信仰している朝長作右衛門は、日本にたった一人残った宣教師であるフェレイラをかくまっていました。朝長が切支丹ではないかと怪しんだ井上らは、計略にかけて彼を捕縛し、「穴吊り」という世にも残酷な拷問にかけ、本丸のフェレイラをおびき寄せるに至ります。そこでフェレイラは神の御心に触れ、触れたからこそ自ら踏み絵を踏み、棄教を決断する…そして小説『沈黙』へとつながるわけです。
ドラマの軸は、神への信仰を選ぶか、それとも恩人や恋人の命、あるいは村の共同体を守るかという葛藤です。フェレイラがどんな苦境に立たされても神は救いの手を差し伸べることはありません。そうしてくると、人間の神に対する考え方が分かれていきます。フェレイラはあくまで神の存在を疑わず、その神がなぜいつまでも沈黙を守っているのかに苦しみます。一方で村人たちは、いつまでも助けてくれないことから、神の不在を意識し始めるのです。ここのところが遠藤が生涯を通じて書き記した「日本人にとってのキリスト教とはなにか」という問題につながるのではないでしょうか。
終幕、フェレイラを「転ばせた」(キリスト教を捨てさせた)井上筑後守は言います。
思えばそこもとは決して余に負けたのではない。この日本と申す泥沼に負けたのだ。だがこの日本の泥沼も決して悪いものではないぞ。それに体を浸しておればやがては泥の心持よい温かさにもなれる。切支丹の教え、あれは炎だ。炎のように人を焼きこがす。だが、この日本のぬるさはやがて、そこもとを眠らせようぞ。(『黄金の国』第三幕 第四場)
泥のぬるさとは、まさに日本を的確に形容する言葉です。正面切った対立や議論ではなく、目に見えない意識に絡めとられ、ずぶずぶと風土の中に沈んでしまう。それが共同体を維持するのにかなり効果的に機能しているところが「日本らしさ」でもあります。
そういえば、イーロン・マスクがTwitter社を買収し、社員に長時間のハードワークを受け入れるか、それとも退職するかを迫っているとのこと。これが新聞で「踏み絵」と呼ばれていました。内実はよく知りませんが、これも日本の企業じゃあまり起こらなそうな改革ですね。大変革しようとしても「まあまあ、イーロンちゃん、気持ちはわかるけど、社風ってものあるからさ・・・」なんて言われて、いつのまにかうやむやになってしまいそうです。今回はそんな日本らしさを感じる戯曲でした。
寒くなってきました。いつの間にやら長袖のシャツを引っぱり出し、コートを着込み、マフラーもいるかなとゴソゴソやっていると、埃が舞って咳が止まらん。と思ったらコロナでした。わたしもついにやられてしまいました。みなさんもお気をつけて・・・。
(松山)