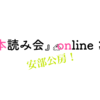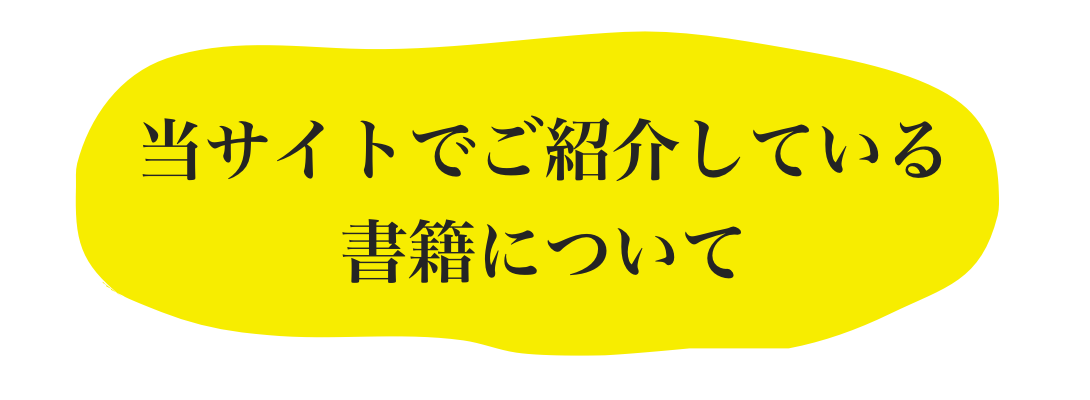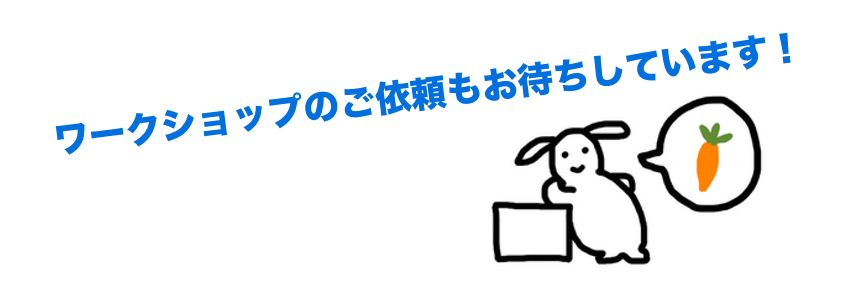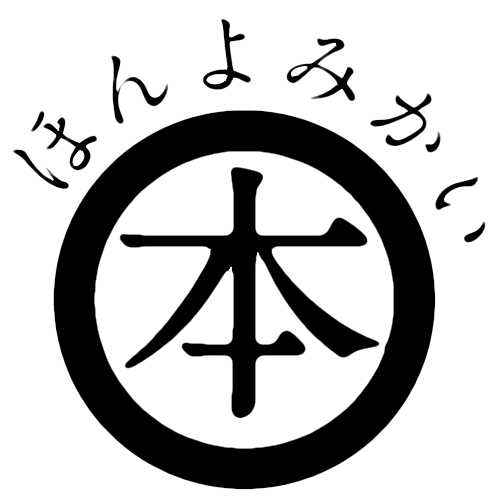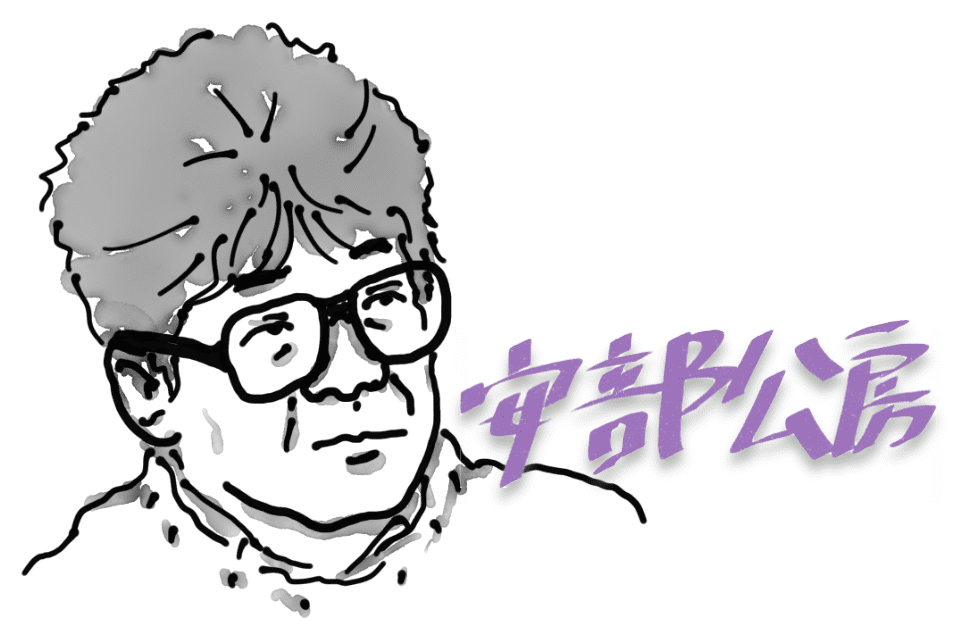
決してコロナのせいというわけでもないのですが、前回『本読み会』からずいぶんと間が空いてしまいました。しばらく戯曲を読まないと「ギギギギ…」と身体が禁断症状を起こしますので、ここでギギっと腰を上げました。テキストは安部公房の『友達』。昨年末の「忘本会」で一部だけ読んだところ好評だったので、これを機に全編読み通してみたくなりました。
会社員とおぼしき男の家へ、突如9人の家族が押しかけてくるという強引な幕開け。うろたえる男は強盗だと警察に訴えるも、「家族」の醸し出す牧歌的な雰囲気に飲まれてそのまま居座られてしまいます。あれよあれよというまに主導権を握られた男は、逆に家から逃げ出そうとするも、今度は家族たちに監禁され、最後には毒殺されてしまいます。ドタバタコメディの顔をして始まるものの、次第に薄気味の悪いドラマへと移り変わる安部公房ワールド全開の戯曲です。参加者の中からも「怖い戯曲」との感想が漏れ聞こえてきます。
男がくり返し訴えるのは、「おねがいだから、ほうっておいてくれ!」
しかし家族の理屈は、「一人ぼっちは、いけないわ。」
これではいつまでたっても交わることがありません。『友達』が発表されたのは1967年。このテーマは古代からSNS時代までずーっと平行線を取り続けている大問題です。今だと「ひきこもり」などを連想しそうですが、主人公の男は仕事にも就いているし、婚約者もいる。それでも、個と集団の対立から逃れることはできません。
とりわけタチが悪いのは、家族の行動は悪意からではなく、純粋な善意から起こっているところ。「孤独な人間を見捨てておけない」と9人家族は迫ります。これに抗う男の主張は、大家さんや警察など、その他社会の人間から理解されず、集団へ飲み込まれていかざるをえません。ここでタイトルにつながり、「友達なんだから」という善意からなる連帯感が、個人を殺してしまう寓話となりえているのです。
ところが、第2幕になるとこの構造が変化していきます。
第2幕は男が監禁されてからしばらく経ったあとのようですが、ここには「男対家族」の単純な関係はもうありません。男を取り込んでしまったあと、家族はその中で男を巡って対立を始めるのです。とくに顕著なのは、肉体的な欲求を男にむける長女と所有欲を満たすために男を毒殺する次女の対立です。
「友達」という連帯の中で熾烈な争いが繰り広げる姿は、当時の学生運動や共産党革命運動をモチーフにしたものかもしれません。第2幕では大勢が茶の間でガヤガヤというよりも、密室で取り交わされる取引、陰謀、裏切りといった濃密な対話劇に移行します。
SNSの普及もあって、いまは「孤独だけど、つながっている」といえる時代なのでしょうか。ひきこもりや孤独死といった問題が浮上する中、人と人とのつながりによって互助する姿が取りざたされますが、『友達』はそのつながりの孕む危うさに光を当てているような戯曲です。
戯曲を読むと上演が観たくなる『本読み会』…と思ったら、今年9月にシス・カンパニーが『友達』を上演しますね。熾烈なチケット争奪戦になりそうですが、観に行った人はぜひまた『本読み会』で感想を聞かせてください。
(松山)