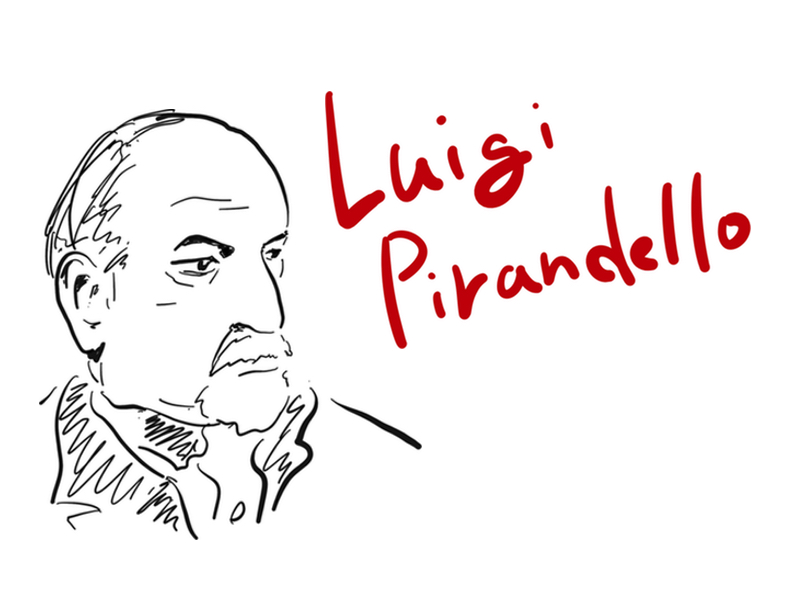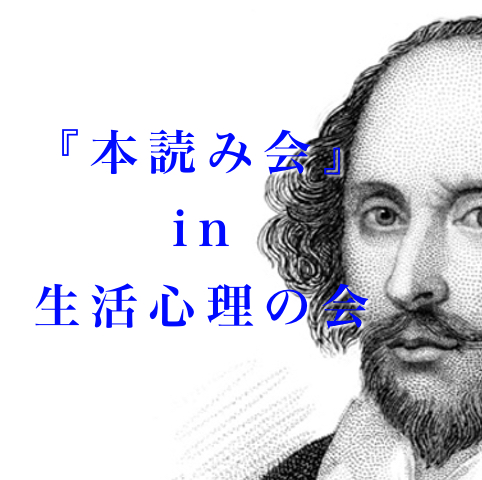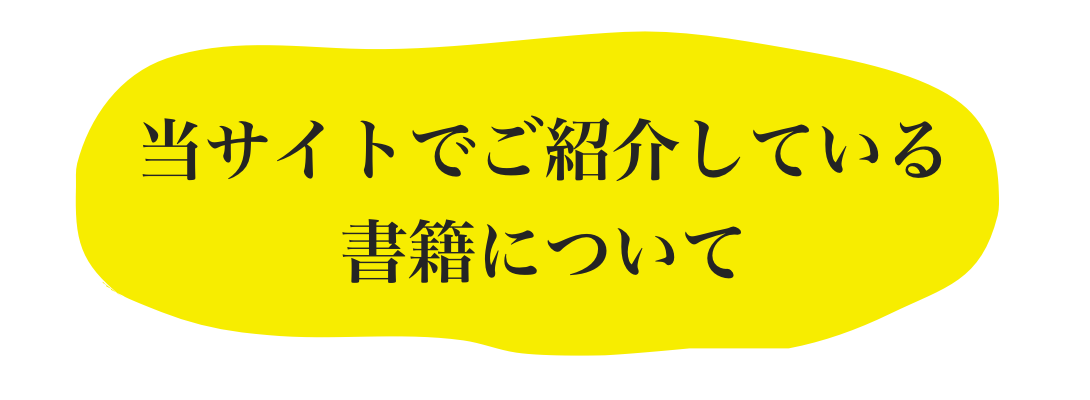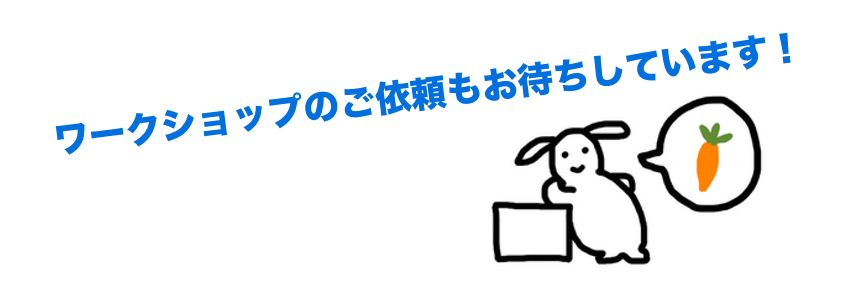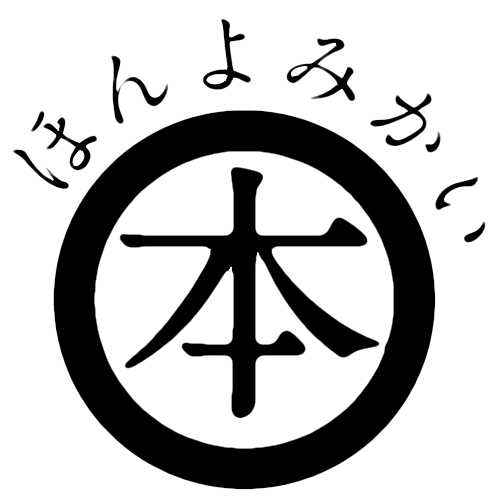『本読み会』にしては珍しい夜開催でした。夜になっても気温が下がることはなく、Yシャツが肌にまとわりつくような暑さです。今回はアメリカ演劇不滅の金字塔、アーサー・ミラーの『セールスマンの死』に挑戦です。暑くてイライラしながら読むくらいがちょうどいい戯曲かもしれません。
『本読み会』にしては珍しい夜開催でした。夜になっても気温が下がることはなく、Yシャツが肌にまとわりつくような暑さです。今回はアメリカ演劇不滅の金字塔、アーサー・ミラーの『セールスマンの死』に挑戦です。暑くてイライラしながら読むくらいがちょうどいい戯曲かもしれません。
当時、新進気鋭の劇作家だったアーサー・ミラーによって『セールスマンの死』が発表されたのは1949年。日本はGHQ主導の下で戦後復興にあえいでいた時代でしたが、第二次世界大戦に勝利を収めたアメリカは早くも次なる時代、次なる戦争へと歩を進めていました。
この戯曲の底には、古きアメリカと新しきアメリカの間に起こる不協和音が絶えず流れています。
主人公は、かつて腕利きのセールスマンだったウイリー・ローマン。物語は終始ウイリーのごく個人的な描写で進行します。昔のお得意様は次々と引退し、今では月々のローンも払えない始末。勤め先に掛け合ってみるも、代替わりした若社長には相手にされず。家に帰ればいい年をしてうだつの上がらない息子たちがくすぶっており、ウイリーに寄る年波は次第に彼を追い詰めます。
そのストレスが彼を誘うのは、過去への幻想でした。もう戻らない古き良き時代、そしてウイリーがかつて目標として届かなかった兄や伝説のセールスマン。進化と発展の思考、そして自己顕示欲と虚栄心にとらわれるウイリーは、自分がもう枯れていくだけの古木だということを受け入れることができません。その葛藤は自分のみならず、息子たちへの暴力的な期待という形でも現れ、妻のリンダは崩壊していく夫を静かな覚悟の中で見守っています。
この戯曲が見事なのは、劇中があまりにも濃密なため、劇の外側、つまりこのドラマが始まる前の人間関係が浮かび上がってくる点でしょう。ウイリーや息子たちの歪んだ思考や人格は一体どこから来たのか、家庭や職場でこれまで起こったであろう問題に、読み手は自然と思いを馳せ、目の前で展開される対話の「向こう側」を読んでいます。そして、読みながらある時に気づくのです。「向こう側」というのは決して過去だけではなく、未来も含むのではないか。ドラマが終わった後も、この負の連鎖は繰り返されるのではないかと。優れた戯曲には、「このドラマは本当に終わったのだろうか」という独特の読後感があるものです。
また、アーサー・ミラーは視覚的・聴覚的な演出を随所に組み込んで戯曲を進めています。読む前はいわゆる写実主義的な近代劇という印象が強かったのですが、登場人物を象徴するテーマ音楽、フルートの音、赤い光線、月の光などが台詞と溶け合って、文学ではなく演劇作品としての強度を高めているのが印象的でした。ちなみに、『セールスマンの死』初演の演出はあのエリア・カザンです。まさに、アメリカが独自の演劇文化を花開かせていく過程でなくてはならない作品だったことがしのばれます。
ウイリー・ローマン役は、日本では滝沢修そして仲代達矢の持ち役として長く演じられてきました。私も高校生の時に観た仲代達矢版の舞台は強烈に覚えています。そんな『セールスマンの死』が来たる2018年11月、神奈川芸術劇場において長塚圭史演出、風間杜夫主演で久しぶりに上演されます。
「本を読んだら劇場へ、舞台を観たら本を手に」とは、ハヤカワ演劇文庫のキャッチコピー。そういえば『セールスマンの死』は、ハヤカワ演劇文庫の第一号として世に出された戯曲でもありました。まさに、キング・オブ・戯曲。
(松山)